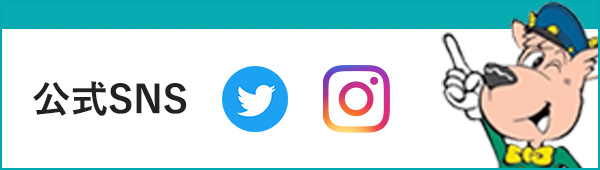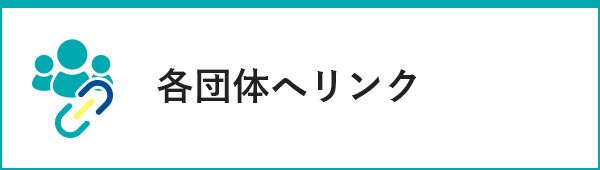更新日:2025年7月3日
ここから本文です。
聴覚に障がいのある方の運転免許取得等について
第二種免許取得を考えている方
平成28年4月1日から、補聴器を使用すれば両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるといった、運転免許証の免許の条件等の欄に「補聴器」の条件が付されている方でも、第二種免許を取得することができるようになりました。
- 第二種免許の免許試験を受けるためには、21歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許を現に受けており、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上などが必要となります。
- 第二種免許取得を考えている方は、ご相談ください。
補聴器条件の方が取得できる免許の種類について
- 第二種免許を含め、すべての免許を取得することができます。
- ただし、運転免許証に「補聴器」条件等が付与となるため、運転する際は「補聴器」を装着しなければなりません。
聴覚に障がいのある方
両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであることとする適性試験の聴力を満たさない方であっても、一定の条件のもと、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車の運転免許を受けることが可能です。
- 詳しくは、特定後写鏡の取付・聴覚障害者標識の表示について(PDF:165KB)をご覧ください。
条件など
1.特定後車鏡条件(ワイドミラー、補助ミラー)
聴覚に障害のある方が、準中型自動車又は普通自動車を安全に運転するためには、特定後写鏡を適切に活用することにより、後方視野を十分に確保し、車両斜め後方の死角を解消することが必要です。
具体的には、後方から緊急自動車が接近してきた場面や通常の後写鏡では死角となる斜め後方(右ハンドル車にあっては左斜め後方を、左ハンドル車にあっては右斜め後方をいう。)を原動機付自転車が走行しているときに、当該原動機付自転車の側に進路変更しようとする場面等において、当該緊急自動車や原動機付自転車を特定後写鏡を適切に使用して確認することができるものです。
なお特定後写鏡は、準中型自動車又は普通自動車を運転する場合は必要ですが、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転する場合は不要です。
2.特定後車鏡の規格
ワイドミラー(車室内において使用)
ワイドミラーについては、準中型自動車又は普通自動車のルームミラー等に取り付けるなどして、運転席から後面ガラスを通して後方を確認でき、運転席より後方の側面ガラスを通して斜め後方を確認できるものが目安です。
特に、自動車の進路を変更しようとするときに、後面ガラスと側面ガラスの間にある柱(ピラー)等より前方にある側面ガラスを通して斜め後方を確認できるものでなければなりません。
補助ミラー(サイドミラーに取り付けて使用~貨物自動車等)
補助ミラーは、準中型自動車又は普通自動車で荷物により後ろが見えない貨物車などの左右のサイドミラーに取り付けることで、自動車の後方の視界を確保することができる鏡のことです。
- 運転席補助ミラーは、後方を走行する緊急車両の赤色警光灯を確認できるものであること
- 運転席と反対側の補助ミラーは、標準ミラーによる視野を補うものであること
が基準となります。
3.聴覚障害者標識の表示
準中型自動車又は普通自動車を運転する時は、前と後ろの定められた位置に聴覚障害者標識を付けることが必要です。
なお、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転する場合には、表示は不要です。
補聴器を条件とした運転免許をお持ちの方
補聴器を条件とする運転免許を現に持っており、補聴器を使用しない状態で運転を希望する方は、総合交通安全センターに「臨時適性検査」を予約し、指定された日に臨時適性検査及び安全教育を1時間程度受講することにより、運転免許の条件変更が可能です。
運転適性相談窓口
公安委員会では、運転適性相談窓口を開設し、運転免許の取得についての相談を随時受け付けております。
聴覚に障がいがあり、運転免許取得をお考えの方、補聴器を条件とする運転免許をお持ちの方で補聴器を使用しないで運転を希望する方は、ご相談ください。
その他、この件について詳細をお知りになりたい方もご連絡ください。
- 受付日
月曜日~金曜日の平日(祝日及び年末年始の休日は除く。) - 受付時間
午前8時30分~午後5時15分まで - 場所
山形県総合交通安全センター試験係
各警察署交通課窓口