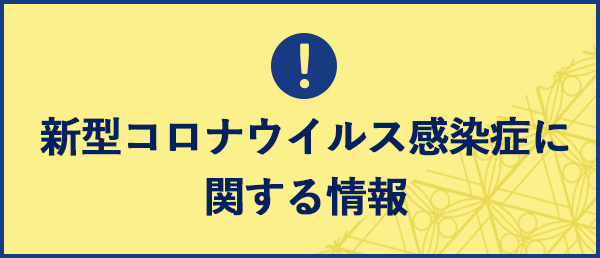更新日:2025年7月31日
ここから本文です。
令和7年8月30日から9月5日までは「建築物防災週間」です!(令和7年度秋季)
期間中の主な取組内容
吹付けアスベストの飛散防止対策に関する使用実態把握の徹底等について
以下の方へ、アスベスト安全対策に関する指導を行います。
1.調査報告がない建築物の所有者など
2.吹付けアスベスト等が使用された建築物の所有者など
定期報告の提出がない建築物等への指導
建築基準法第12条に基づく定期報告の提出がない建築物などの所有者又は管理者に対し、報告の提出と建築物などの適切な維持管理について指導を行います。
定期報告制度の詳しい内容は、建築物や建築設備に関する定期報告をご覧ください
住宅・建築物の耐震化(耐震診断・耐震改修)の促進
令和6年能登半島地震では、石川県内の比較的被害の大きかった7市町において、耐震改修の補助制度を活用した住宅については倒壊したものがなく、耐震改修の有効性が確認されたところです。
昭和56年6月に建築基準法の耐震規定が大きく改正され、現在の新耐震基準となりました。昭和56年5月以前に着工した住宅は、古い耐震基準(旧耐震基準)で建築されており、耐震性が不足している可能性があります。
詳細は、耐震診断・耐震改修のすすめをご覧ください。
また、山形県では、地震から命を守るため、住宅の状況に応じた補助制度を設け、耐震性向上を支援しています。
詳細は、命を守る住宅改修支援についてをご覧ください。
窓やベランダからの子どもの転落防止について
子どもが窓やベランダから転落する事故が、多く発生しています。
小さい子どものいるご家庭においては、ベランダや窓の近くに足場になるようなものを置かない、エアコン室外機の置き場所に注意する、窓や網戸に補助錠を付けるなど、事故が起こらない環境づくりに努めてください。
詳細は、子どもの転落事故防止についてをご確認ください。
建築物やエレベーター等の事故防止について
1事故の再発防止について
建築物や昇降機等における事故が発生しています。同様の事故を防止するため、国土交通省ホームパージなどにおいて、これまでに発生した事故の概要や対策などについて公表されています。
詳細は、建築物・昇降機・遊戯施設等に係る事故情報についてをご覧ください。
2エレベーターの扉が開いたまま走行する事故の防止について
戸開走行保護装置とは、扉が開いたまま走行した場合に自動的に籠を制止する装置です。
平成21年9月28日以降に設置されたエレベーターには、戸開走行保護装置の設置が義務付けられていますが、設置義務より前に設置されているエレベーターには戸開走行保護装置がついていないものが多くあり、扉が開いたまま走行する事故が発生しております。
事故を未然に防ぐには、戸開走行保護装置を設置することが有効です。当該装置を設置していない所有者におかれましては、戸開走行保護装置の設置をご検討ください。
詳細は、エレベーターの扉が開いたまま走行する事故防止についてをご覧ください。
建築物に付属するブロック塀等の安全対策の推進
地震による塀の倒壊は、死傷者を生じる恐れがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたす恐れがあり、その安全対策は極めて重要です。
県民の皆様には、ご自身が所有又は管理している塀について安全点検をお願いいたします。
詳細は、塀の安全点検のお願いをご確認ください。